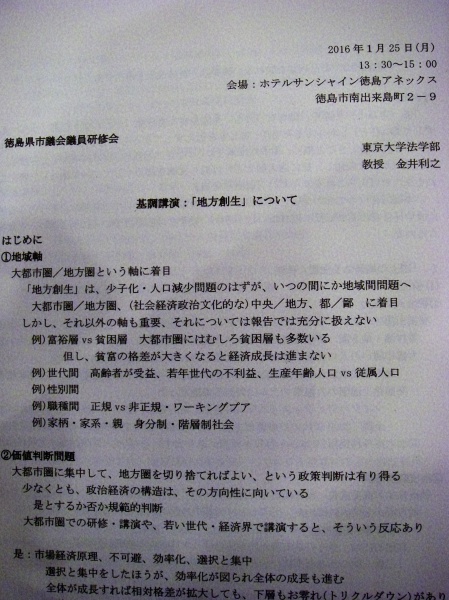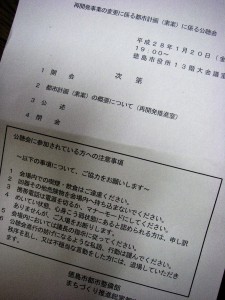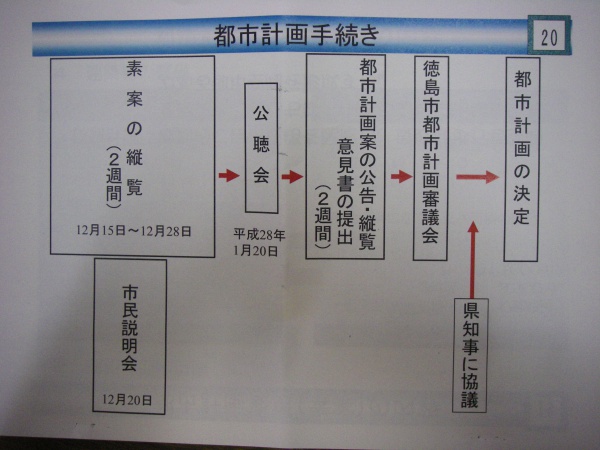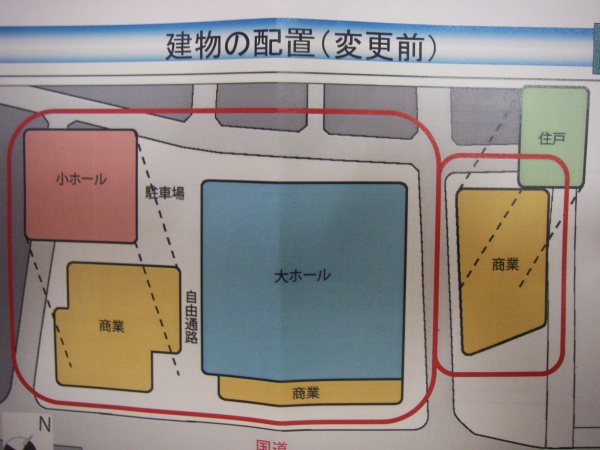更生保護女性会の目的
人間だれもが人として尊重され、自分らしく生きたいと願っています。
たとえ、非行や犯罪に陥った人でも同じです。
私たちは、まずこれを活動の基本にすえ、一人ひとりが人として尊重される社会を目標とします。
また、同時に社会は、みんなでつくり、みんなで支えあっていくものであり、人と人の連帯なくして成り立ちません。
私たちは、人間尊重と、お互いに他を思いあい、連帯しながら、だれもが心豊かに生きられる明るい社会づくりをめざします。~以上ネットから~
地震の救援募金うけつけ
ホット・リンク
見田おさむtweets
Could not authenticate you.-
最近の投稿
- 喜寿にあたって~
- はや今年も「師走」となりましたね。12月の雑草の庭の彩りをご紹介です。
- 徳島も梅雨入り~雑草の庭と紫陽花です。
- 午前2時半、台風が近づいているようですが、今のところ雨風ともその気配はありません。この時間に起きているということは、なかなか寝付けないということですが、特に翌日の予定があるわけではないので「自由時間」です。徐々に慣れていくでしょうね。
- 今、枇杷がスズナリになっています。少し小粒ですが、甘さは抜群です。「ご近所の皆さん。ご自由にお取りください。」いつもの張り紙を明日枇杷の前の塀に張り出します。
- 昨日は1時間、今日は1時間半、吉野川南岸を歩きました。ダイエット開始です。さて、どうなることやら?
- 徳商の同窓会が近づいてきました。何を着て行こうか~コーデネィトの必要もないのに、気にしている自分がいます。何年ぶりかな~
- 雑草の庭の主役は「フキ」です。フキの煮つけ・佃煮を作っています。それから、タケノコをいただきましたので、米ぬかであく抜きです。なんとかなりそうですよ。では。
- 毎年、「連休」は関係なし~4/28~5/7の10連休の方もいらっしゃるとは思いますが、私の場合、5/1のメーデー集会と5/3日の憲法記念日の街頭宣伝と講演会は労働運動に参加してからの必須行事となりました。
- 5月3日は憲法記念日~毎年「憲法を生かし守ろう」のアピールを行いました。
最近のコメント
- 2023年3月20日、徳島市議会3月議会が閉会しました。4月には一斉地方選挙、徳島市議会議員選挙が控えており、私の後任として平岡やすひと氏が市議会議員に立候補します。まだ任期は4月いっぱいありますが、ひとまず3期12年間をしめくくる議会となりましたので、3/10個人質問の末尾でこれまで支えていただいた皆様への御礼の言葉を述べさせていただきました。ありがとうございました。 に がんちゃん より
- 2/9明るい徳島市をつくる市民連絡会総会~市政に対する態度を表明しました に 佐藤 美智子 より
- 2/9明るい徳島市をつくる市民連絡会総会~市政に対する態度を表明しました に 鈴江美和子 より
- 日産キューブのエアミックスドアの異常で5万円とは~ に テッポウ厳禁 より
- ごみゼロフォーラムの公開アンケートに2/22付で日本共産党市議団連名で回答させていただきました。 に ごみゼロフォーラム実行委員会代表 福井 紀久子 より
2025年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 アーカイブ
カテゴリー
 しんぶん赤旗
しんぶん赤旗