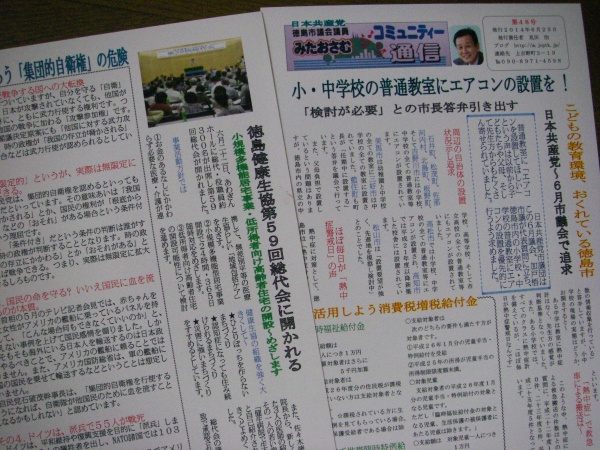その1.海外で戦争する国への大転換
「自衛」と名がついていますが、自分を守る「自衛」とは無縁です。日本が攻撃されていなくても、他国が攻撃されたときに、ともに武力行使する権利です。つまり、日本が他国の戦争に加わる「攻撃参加権」です。与党協議の中で自民党が示した閣議決定原案には「我国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、「我国の存立が脅かされ」「明白な危険がある」と判断した場合は武力行使が認められるとしています。これは憲法9条のもとで専守防衛に徹してきた日本の安全保障政策の大転換です。
その2.「限定的」というが、実際は無限定に拡大解釈できる。
政府や自民党は、集団的自衛権を認めるといっても「限定的」だといっています。その意味あいは「我国の存立が脅かされる」とか、国民の権利が「根底から覆される」などの「明白な危険」がある場合という条件付だからという理屈です。
しかし、「条件付き」だという条件の判断は誰がするのか、時の政権が判断することとなります。時の政権が「国の存立にかかわる」とか「明白な危険」と判断すれば戦争できる。つまり、実際は無限定に拡大解釈できるしろものです。
その3.国民の命を守る? いいえ国民に血を流させるのが本質。
安倍首相の5月のテレビ記者会見では、赤ちゃんを抱いた女性がアメリカの艦船に乗っているパネルを持ち出して、「こんな場合何もできなくていいのか」と、ありえない事例を上げて国民感情を煽りました。しかし、そもそも海外にいる日本人を輸送するのは日本政府のやるべきことで、アメリカの艦船に頼ることではありません。また、アメリカ国防総省は、軍の艦船に他国の国民を乗せて輸送するなどということは想定していません。
自民党石破茂幹事長は、「集団的自衛権を行使するようになれば、自衛隊が他国民のために血を流すことになるかもしれない」と認めています。
その4.ドイツは、派兵で55人が戦死
ドイツは、平和維持や復興支援を目的に「派兵」しましたが、55人の犠牲者を出し、NATO諸国では1032人が犠牲となっています。
かつて、政府はアフガン戦争やイラク戦争でアメリカの要請に応えて、自衛隊を派兵しましたが、憲法9条によって①武力行使はしてはならない。②戦闘地域にいってはならない。という二つの歯止めをかけ、非戦闘地域での「後方支援」に限られていました。集団的自衛権の行使は、この歯止めを無くし、際限のない戦争への道に足を踏み入れることになります。